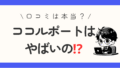はじめに
「障害者手帳を持っているけれど、実際にどんな制度が使えるのかわからない」
「福祉の仕事をしているけれど、利用者さんにどう説明したらいいか悩む」
そんな声をよく耳にします。
実は、障害者手帳や関連する公的制度を正しく理解して活用するだけで、生活費を大きく抑えたり、収入を安定させたりできることがあります。ところが、制度が複雑で知らないまま損をしている人も少なくありません。
この記事では、障害者手帳の種類ごとのメリットや、公的制度によるお金の支援について、できるだけわかりやすく整理しました。求職中の方、生活に不安を抱える方、福祉職として支援する立場の方に役立つ内容になっています。
障がい者手帳とは?3種類の基本と対象者
まずは、制度の入口である「障がい者手帳」について確認しましょう。
障害者手帳には大きく3種類あります。それぞれ対象や等級、受けられる支援が異なるため、まずは違いを整理しましょう。
| 手帳の種類 | 正式名称 | 対象 | 等級・区分 | 主な支援・メリット | 更新の有無 | 更新の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体障害者手帳 | 視覚・聴覚・肢体・内部障害 | 1級〜6級 | 医療費助成、交通割引、税制控除、福祉サービス | あり | 5〜10年(手帳に記載) |
| 療育手帳 | 療育手帳(A/B区分) | 知的障害 | A(重度)、B(中度・軽度) | 税制優遇、医療費助成、福祉サービス、交通割引 | あり | 5年ごとや年齢で更新(自治体差あり) |
| 精神障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、発達障害など | 1級〜3級 | 医療費助成、交通割引、税制優遇、就労支援 | あり | 1〜5年(障害の程度・自治体により変動) |
身体障害者手帳
- 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害などが対象
- 1級から6級まで区分
- 主に医療費助成や交通割引、福祉サービス利用で有効
→障害が「永続的に」続くとみなされることが多く、更新期限が長い。
療育手帳
- 知的障害がある方が対象
- A(重度)、B(中度・軽度)と区分される場合が多い
- 税制優遇や手当、割引制度などに使える
精神障害者保健福祉手帳
- 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害などが対象
- 1級から3級まで
- 就労支援や税制優遇、公共サービス割引などが適用
→症状が短期的に変わるとみなされやすく、更新期限が短い。
これらの手帳は「福祉サービス利用のパスポート」と言える存在です。単なる証明書ではなく、経済的な負担を軽減してくれる重要なキーになります。
医療費の助成制度
生活に直結するのが医療費。障害者手帳を持つことで、以下の制度を利用できます。
自立支援医療(精神通院医療)
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人に多く利用される制度
- 医療費(診察・薬代)が1割負担に軽減
- 例えば、月1万円以上かかっていた通院費が3000円程度になることも
→心療内科・精神科に通院していれば、障害者手帳を持っていなくても利用できます。利用可否は診断名によって変わるため、早めに受付もしくは主治医に相談しましょう。
重度心身障害者医療費助成制度
- 各自治体が独自に実施
- 身体障害者手帳1・2級や療育手帳A判定などが対象
- 医療費自己負担を全額助成(無料になる場合も)
高額療養費制度
- 健康保険加入者なら誰でも利用可能
- 1か月に医療費が一定額を超えると払い戻しがある
- 障がい者の場合、ほかの制度と併用できるケースも多い
ポイント:医療費助成は自治体ごとに差があります。住んでいる市区町村のHPで必ず確認しましょう。
交通費の割引制度
日常生活や通勤にかかる交通費も大きな負担ですが、障がい者手帳を持つことで割引が適用されます。
公共交通機関の割引
- JR、私鉄、地下鉄、バスなどで運賃が半額になる場合あり
- 身体1種・精神1級などは介護者1名も同じ割引を受けられる
- 通勤定期券にも割引が適用されるケースがある
タクシー料金割引
- 一部のタクシー会社では1割引が標準
- 利用時に手帳を提示するだけ
航空機・フェリーの割引
- ANAやJALでは国内線運賃が約2割〜5割引
- フェリーも半額になる路線が多い
ポイント:特に通勤や通学で長距離を移動する方にとって、年間数万円単位の節約につながります。
年金・手当の制度
収入の安定を支えるのが「年金」や「手当」です。
障害年金
- 国民年金・厚生年金に加入中に障害を負った場合に受給可能
- 障害基礎年金:1級 約10万円/月、2級 約8万円/月(令和6年度目安)
- 障害厚生年金:給与水準に応じて上乗せあり
- 精神障害や発達障害も対象になる
→申請がとっても大変です。ですが、認定されれば安定した収入が得られますので、一度は検討をお勧めします!申請を社労士に代行してもらうことも出来ます。
特別障害者手当
- 在宅で重度障害のある方が対象
- 月額 27,980円(令和6年度)
障害児福祉手当
- 20歳未満の重度障害児が対象
- 月額 15,690円(令和6年度)
自治体の独自手当
- 例えば「福祉手当」「心身障害者手当」など名称はさまざま
- 月数千円〜数万円の支給がある自治体も
ポイント:申請しなければ受けられない制度が多いため、知らずに損をしている人が多い分野です。
就労支援とお金のメリット
就職や働き方に関しても、障がい者制度には経済的メリットがあります。
障害者雇用枠での就職
- 企業に法定雇用率(2.5%)があるため、安定した採用ルート
- 就労移行支援やハローワークを通じて職探しが可能
就労継続支援A型・B型
- A型:雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる
- B型:雇用契約はないが、工賃(平均月額約1.6万円)が支給される
就労にまつわる助成金(企業向け)
- トライアル雇用助成金、職場適応援助者(ジョブコーチ)制度
- 福祉職の方が知っておくと、利用者への提案の幅が広がる
税金・公共料金の優遇制度
障がい者手帳を持っていると、税金や公共料金にも優遇があります。
所得税・住民税控除
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 同居特別障害者控除:75万円
相続税・贈与税の特例
- 障がい者が相続人の場合、基礎控除額が増える
自動車税・自動車取得税の減免
- 通院や通勤に必要な車を所有している場合に有効
公共料金の割引
- NHK受信料の全額または半額免除
- 電気・ガス・水道料金の減免(自治体ごとに異なる)
制度を使いこなすコツ
せっかくの制度も、「知らない」「申請していない」ことで使えない人が多いのが現実です。
- 自治体の障がい福祉課・障害者相談支援センターに相談する
- 福祉職や医療機関と連携して手続きを進める
- 障がい者手帳を提示する習慣をつける(交通機関・公共サービスなど)
- 制度は毎年変わるため、最新情報をチェックする
まとめ
障がい者手帳を活用すると、医療費・交通費・税金・年金・手当など、生活のあらゆる場面で経済的なメリットを得られます。
しかし、制度は複雑で自治体によっても差があるため、「知っているかどうか」で損得が大きく分かれます。
- 医療費助成 → 通院・薬代が1割や無料に
- 交通費割引 → 定期代や旅行費用が半額に
- 年金・手当 → 毎月数万円の安定収入に
- 税制優遇 → 所得税・住民税の軽減に
「手帳を取ったけれど使い方がわからない」という方は、まず医療費助成や交通費割引からチェックしてみましょう。
そして、支援者の立場にある福祉職の方は、これらの情報を利用者さんに伝えることで、安心して生活を送るための大きな支えとなります。